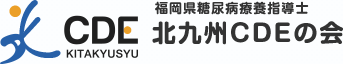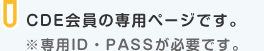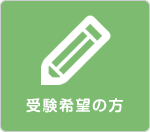隠し味の酒粕
DATE:2024.04.01
最近「加藤家の食卓」という本を買いました。ご存じの方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、加トちゃんの為に、奥様の綾菜さんが医師や栄養士の方々に指導を受け、考案した「万能 氷だし」と氷だしを使ったレシピが載ってます。濃い味を好んでいた加トちゃんは、何にでも後からお醤油をかける方だったそうです。ところが年齢と共に腎機能が落ち透析?となりそうだったところ、綾菜さんの毎日のお料理のお陰で随分健康になられたとの事。「減塩食は味気ない」けど健康の為には「仕方ない」というイメージがありますし、「出しやスパイスを効かせたら良い」ともよく聞きますよね。同じような感じだろうな・・・と、あまり期待せず読んでみました。
私は加藤家の回し者では有りませんが、このレシピを試して、「酒粕」がいい仕事をしてる!!!と感じ、皆さんにお伝えしたくて書きました。
酒粕は身体に良いとか、寒い冬にはかす汁があったまるとか、よく耳にします。何度か料理に使った事も有ります。しかし、お酒の美味しさが未だ分からない私は、どうも酒粕のあの独特の香りが鼻に残って、これまで美味しい料理にまで到達したことが無かったのです。しかし、この「氷だし」のレシピに酒粕が入っているのです。だしの取り方も、普通はNGの、かつおをしっかり押し付けて濾したりと、???ですが、とにかく本に忠実に作ってみました。そして、その氷だしを使って、これ又本のレシピ通りにハンバーグや回鍋肉を作ってみたのです。結果はむ!む!む!オ・イ・シ・イ!しょっぱく無いけどおいしい!?この微かに感じるうま味は?何だ?・・・酒粕だあ!酒粕が酒粕の存在を主張せずに風味というか、うま味というか、食思を刺激するんです!
ちょっとカンゲキしました。料理も「ゲンエンシテマス!」的主張が無いんです。
もう少しこの本でマスターしたら自分のレシピ作りにチャレンジしてみようと思っています。
年度変わりです
DATE:2024.03.27
こんにちは。桜の便りも耳にするようになりました。「お花見」の予定のある方もおられるかと思います。
「桜の開花」や「桜前線」がニュースになり、日本中が少し浮足立つようなこの季節は、外国から見るとちょっと驚きなんだとか、まあ、そう言われればそうなんですが、僕も楽しみにしている一人ではあります。
さて、年度が変わりますが、異動や退職、就職、転居等で会員情報の変更のある会員の方は、ログインして会員情報の変更をお願いしますね。ログイン方法がわからない方はホームページの「関連資料」にある「ログイン方法について」を参照してください。会員情報が古いままですと、会からのお知らせが届かない場合がありますので。よろしくお願いします。M
ヨガ
DATE:2024.03.08
ヨガに通いはじめて8年目になる。
高校生の頃から興味を持っていたが、あぐらを組むことができない。 自分にはヨガはできないなぁと思っていた。学生の頃禅寺で座禅を受けたことがある。当然あぐらを組めないので正座で受けることになるが、周りの友人等が全員あぐらを組めることに驚いた。当然、ヨガは諦めていたし、その後の生活にもやはり"あぐらを組む"ことはかったし、出来ないことでの支障は全くなかった。
就職後、心療内科の治療の一環で自律訓練法というのがある事を知りここでもヨガの話が出てきた。ヨガは自立訓練の一環なのか?
あぐらはヨガとどう関係するのか?
40歳を過ぎ、頭痛、肩こり、背部痛、冷え性、不眠などあちこち体に支障が出てきて、枕やマトレスを替えたりといろいろ試してもみた。マッサージに行き出したり体の調整が必要、自分でも運動、ストレッチが必要だと実感する様になる。
家の近くにヨガスタジオが出来たのを機にお試しレッスンに行ってみた。
スタジオに入り「呼吸しやすい!」が第一の感想だった。
インストラクターの先生からの指示で右、左、足、手、首など動かすが何と脳トレ!ではないか!
元々心配していたあぐらは"できなければできる範囲でやれば良い"
という事で初めてもう8年経ってしまった。
当初、あぐらは「そのポーズは体操座りですか?」と笑われるほどだったのが今では"何となくあぐら"にみれるくらいに成長している。
ヨガスタジオでは、あぐらだけでなく、"真っ直ぐに寝る"こともできないのを知る。
両肩がマットにつかない、つまり巻き肩がひどい状態だったが、今は何とか肩がマットに付く様にはなった。
ヨガでポーズをとる事をアーサナと言い呼吸がとても大事になる。
今の私がやっているヨガは、瞑想に向かう自律訓練でなくリラクゼーションや健康増進のためのものだと思っている。
インストラクターの先生が、「呼吸〜呼吸してますか〜」と苦しい時に肩に力を入れている時に呼吸を深くする事で肩の力を抜くことができる。
あっ、こういうことか!
ずっと肩に力を入れてた自分がいる!
と思わせてくれる。
スタジオで顔を合わせる方々は私よりうんと若い方々が増えている。
若い頃から肩の力を抜いて今の自分を感じながら仕事していく、生活していくことが出来るなんて何て素晴らしい事だと思う。
長く続けてきてヨガの気持ちよさだけでなく奥深さも感じている。
もっとあぐらを組める様になりたい。あぐらを組んで瞑想もできる様になりたいと思っている。
そんな気持ち良い空間を共にしませんか?
ナマステ
2024年 ウォークラリー スタッフ募集
DATE:2024.03.04
開催期間 2024年5月12日(日)08時~
申し込み期限 2024年4月5日(金)24時まで
開催場所 門司港レトロ地区 旧大連航路上屋
料金 無料
申し込み人数 80人
参加回数 1回
「歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー」スタッフを募集いたします。
・スタッフ募集締切は4月5日(金)ですが、定員80名に達した場合は、早めに締め切る場合があります。
・当日のみの参加も受け付けていますが、極力、事前説明会と両日(4/21、5/12)参加をお願いします。当日のみの参加でイベント参加1回、両日参加でイベント参加2回となりますが、事前説明会(4/21)のみの参加時は、イベント参加とはなりませんのでご注意下さい。
・事前説明会日時:2024年4月21日(日)9時~13時
事前説明会会場:門司メディカルセンター内会議室
・事前説明会では、実際にコースを歩きますので、歩きやすい靴での参加をお願いします。
・執務内容:受付業務・血糖測定・コース誘導・イベント手伝い等
・申し込みは、ホームページよりログインして申し込み下さい。
・当日のみ参加の方は、お問合せからその旨を連絡して下さい。
・当日は、青ジャンバーと名札を忘れないようにお願いします。
・FAX 093-671-5014 横溝内科クリニック
・中止の場合は、前日19時以降にホームページにて告知を行ないます。
糖尿病カンバセーションマップ糖尿病ファシリテータートレーニング
DATE:2024.02.17
関連資料より「糖尿病カンバセーションマップファシリテータートレーニング開催」のチラシをダウンロードできます
・日時 2024年 4月14日(日) 9時30分~16時30分
・場所 白十字病院 いきいきホール
(福岡市西区石丸4-3-1) 092-891-2511
・受講料 条件により異なりますが、福岡県内開催ですので交通費等が通常より低く抑えられる場合があります
・要 事前参加登録
・糖尿病カンバセーション・マップは、数人のグループで、糖尿病に関するこれまでの知識や体験を話し合い、糖尿病について学ぶ、全くあたらしい糖尿病教材です。グループダイナミックスを利用した療養支援のスキルを身につけることができます。ぜひご参加ください!
※詳細はチラシを参照してください